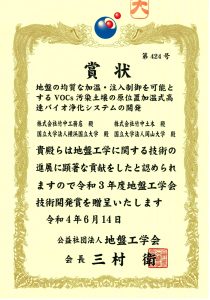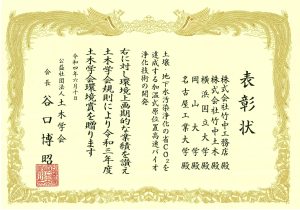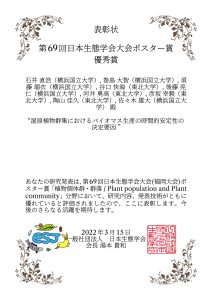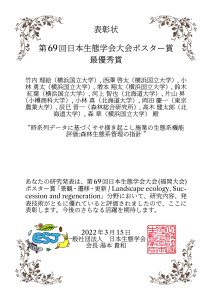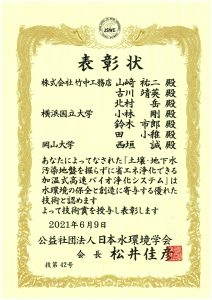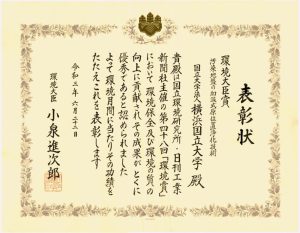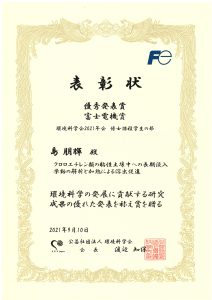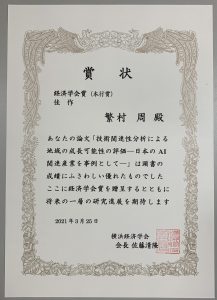プレスリリース
横浜国立大学の佐々木雄大教授は、東北大学の陶山佳久教授、彦坂幸毅教授、ドイツ統合生物多様性研究センター(German Centre for Integrative Biodiversity Research: iDiv)のNico Eisenhauer教授らとの国際共同研究で、山岳湿原に生育・生息する植物および微生物が湿原の機能に果たす役割を評価した論文を発表しました。
青森県八甲田山系に多数分布する山岳湿原群を対象に調査を行い、特定の植物群および微生物群が炭素循環に関わる湿原の機能を支えていることを明らかにしました。さらに、湿原内に異なる植物群および微生物群が含まれるほど、湿原の機能が多様になることがわかりました。山岳域や寒冷地における湿原は、世界の陸地に占める面積は少ないものの、低温・過湿条件によって植物が分解されずに堆積するため、大きな炭素吸収源としての役割を果たしています。
今回の知見は、湿原において、多様で異質な植物群集を保全することで、多様な微生物群集の保全を促進でき、地球環境にとって重要な生態系の機能を維持できることを示しています。
本研究成果は、国際科学雑誌「Journal of Ecology」に掲載されました。
詳しくは、詳細資料をご覧ください。